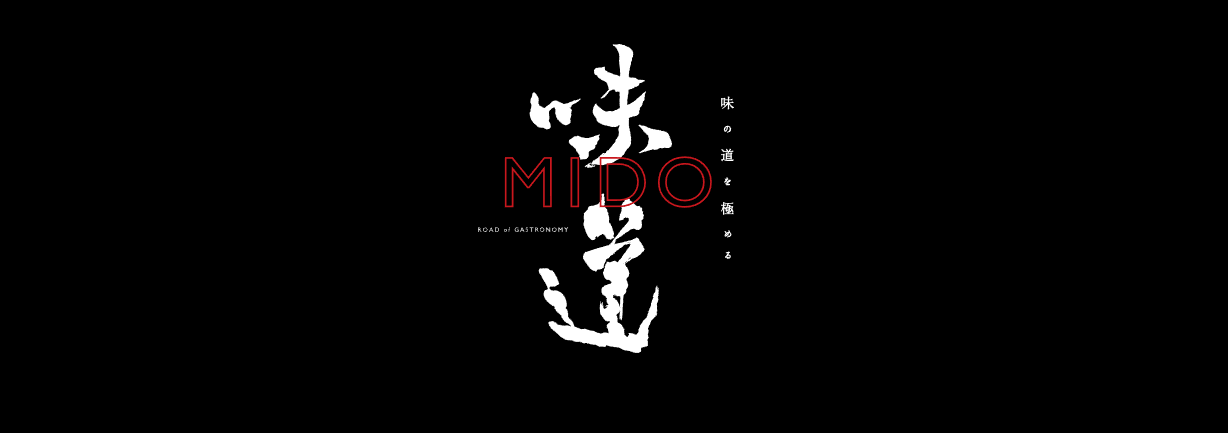日本の誇る食文化を次世代に継承していくために、一流料理人の技術や知識を動画で共有するプラットフォーム「味道」を運営するChef’s Link株式会社。同社は、一般社団法人全日本食学会と協力し、料理人が抱える様々な課題を解決できるプラットフォームの構築を目指しています。
スタートアップ企業にとって、自社のビジョンを具体化できる開発パートナーとの出会いは容易ではありません。同社は当初、開発会社との意思疎通の不備や納期遅延、要件のズレといった課題に直面し、サービスの立ち上げ自体が難航していました。
しかし、Solashiとの協業を開始したことで、柔軟でスピーディーな対応が可能となり、開発が円滑に進むようになりました。結果としてユーザー体験が向上し、サービスの安定運営が実現。現在では、新たな機能開発も順調に進んでいます。
今回は、複数の開発会社との協業を経て、なぜSolashiを開発パートナーとして選んだのか、そしてどのような成果が得られたのかについて、Chef’s Link株式会社 代表取締役社長 高木さんにお話を伺います。
日本の食文化の継承と発展に貢献するため、料理人のための学びの場を動画で提供
――まず、御社の事業について詳しく教えていただけますでしょうか。
高木氏:
私たちChef’s Linkは、一般社団法人全日本食学会と協力し、一流料理人のレシピやノウハウ、そして料理人としての技術や哲学を動画で共有するプラットフォーム「味道」を運営しています。
味道の大きな目的として、日本の食文化の継承と発展があります。食文化を支える料理人は、料理だけでなく経営やその他の業務にも追われ、多忙な日々を送っています。また、若い世代の料理人の方々は修行に多くの時間を割き、広範な知識や新しい技術を体系的に学ぶ機会が不足しているのが現状です。
こうした料理人を取り巻く課題に対して、まずは動画を通じて学びの場を提供することから始めました。動画を通じて、食の技術や哲学を発信することで、料理人の方々をサポートし、新たな成り手の育成に寄与したい、というのが味道の狙いです。
――なぜ動画メディアという形態を選ばれたのでしょうか。
高木氏:
動画メディアを選んだ理由は、まず「映像として後世に技術を残していける」ことに大きな価値を感じたからです。料理の世界には、文章や写真だけでは伝えきれない技術や細かなポイントが数多くあります。こうしたニュアンスを正確かつ直感的に伝えるためには、動画が最も適していると考えました。
また、ちょうどその頃、料理動画市場が急速に発展し始めていました。コロナ禍を経て、料理人や飲食業界の方々がオンラインで技術や情報を学ぶことへの関心も一気に高まりました。こうした市場環境の変化が、私たちの取り組みを後押しする追い風にもなりました。
なお、既存の動画プラットフォームではなく自社メディアを選んだのは、ユーザーのデータを自社で管理・蓄積できるためです。自社メディアを通じてユーザーとの直接的な関係を構築し、将来的なサービス展開や事業の幅を広げる基盤をつくりたかったという背景があります。
現在では、おかげさまで多くの料理人の方々にレシピを提供いただいており、自社ブランドとしてのサービス展開もしやすい環境が整ってきたと実感しています。
成長を支えるスピーディーな対応と適切な提案力
――当初は別の会社に動画プラットフォーム開発を委託されていた、とうかがいました。当時はどのような課題があったのでしょうか。
高木氏:
最初の開発会社は、コミュニケーションや工程管理に問題がありました。たとえば、メッセージの確認に数日、対応の検討に数週間を要していました。さらに、システムが出来上がるはずの時期にも関わらず、要件定義が終わっていないことも後から発覚したんです。
そうしたなか、知人から紹介されたのが島添さんです。最初は現状を打破するために、コンサルティングの立場でご協力いただきました。私はシステム開発の専門家ではなかったので、島添さんに開発会社との定例会議に同席してもらいました。
島添さんからシステム開発の観点からアドバイスをいただき、初期フェーズの開発をなんとか終えることができました。その後、いくつかの小規模な開発案件を通じて、Solashiの高品質な仕事を実感したんです。
――Solashiのどのような点を評価されたのでしょうか。
高木氏:
まず、基本的な仕事の進め方がしっかりしている点です。たとえば、ユーザーからクレームがあった際は、Solashiは即座に初期対応の提案までしてくれます。また、単に開発するだけでなく、事業フェーズに応じた適切な提案をしていただいている実感がありました。島添さんのスタートアップや大企業で培った知見や実績を活かしたアドバイス、事業そのものに共感してご提案いただける姿勢も大きな魅力に感じますね。
たとえば、新しい機能の開発を検討する際も、「100の完成度を目指すのではなく、まずは50で始めてみましょう」とか「20程度の機能で一度検証するのはどうか」といった具合に、その時々の状況に合わせた現実的な提案をしてくれます。私たちの事業の状況を深く理解した上で、スピーディーかつ柔軟な対応をしてくれたので、とても心強かったです。
ユーザー体験の向上で解約率が大幅改善
――開発面での具体的な取り組みについてお聞かせください。
高木氏:
初期フェーズでリリースしたものは、動画を格納して配信する基本機能に限られていました。そのため、第2フェーズでは、ユーザー体験を向上させるための開発を進めることになりました。具体的には、デザインやUIの改善、さらにはリコメンド機能を導入しました。
結果、サービスの解約率は当初の5%から2%にまで改善し、ユーザー体験向上の重要性を実感しましたね。
――ベトナムの開発チームについての印象はいかがですか。
高木氏:
開発のスピードと品質は非常に高いですね。コミュニケーションには時間がかかることもありますが、なによりそれを乗り越える勤勉さがあります。また、新しいことへのチャレンジ精神も旺盛で、事業に対する共感力も高いと感じました。日本人の開発者と比べても、仕事の質は決して劣りません。むしろ、その意欲的な姿勢には、勇気づけられる感じがしますね。
ナレッジプラットフォームへの進化を支える、信頼できる開発パートナー
――今後の事業展開についてお聞かせください。
高木氏:
現在、動画プラットフォームの機能強化に加え、料理人向けのナレッジプラットフォームとしての発展も計画しています。料理人の方々が、難しい専門用語や伝統的なしきたりなどについて、「ここに来れば間違いない」という信頼性の高い情報にアクセスできる環境を作りたいと考えています。
また、動画だけでなく、テキストなどでの情報発信や、検索システムの実装に取り組む予定です。将来的には、料理人の方々が抱えるさまざまな課題を解決できるサービスを展開することで、料理人を目指す人が増えることや、料理に集中できる環境をつくることを目指しています。
加えて、仕入れや経営に関わるサービスのほか、キャリア支援なども視野に入れています。たとえば、老舗料理店の知見や技術を若手料理人に伝えていくような、継承の場を作っていきたいと考えています。
料理人は職人気質で、技を「見て学ぶ」世界です。そうしたあり方を大切にしながら、より多くの方が安心して料理人を目指せる環境づくりに貢献できるプラットフォームを目指していきたいですね。
――最後に、開発パートナーとしてのSolashiの魅力を教えてください。
高木氏:
スタートアップには、「安心して開発を任せられるパートナー」が欠かせません。特に新しい事業機会が生まれた際に、スピーディーかつ柔軟に対応し、具体的な提案を行ってくれるパートナーは、非常に心強い存在です。
また、当社のようなスタートアップでは、サービスの方向性が明確でない段階で開発を進める必要があります。そのため、トラブル発生時に迅速に対応し、ユーザーへの影響を最小限に抑えてくれることが、事業を進める上での重要な要素となります。
事業フェーズに応じた適切な提案をし、スピーディーに対応してくれるSolashiの存在は、私たちの大きな強みとなっています。Solashiは単なる開発会社ではなく、事業の成長をともに考えてくれる欠かせないパートナーですね。

 English
English